躍動するイメージ。
【ART REVIEW】
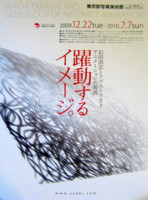
今日は東京都写真美術館で開催中の「躍動するイメージ。石田尚志とアブストラクト・アニメーションの源流」をご紹介します。アニメーション誕生当時の古典的映像装置から現代日本の映像作家・石田尚志の新旧作まで、抽象アニメーションの歴史を幅広く紹介した展示です。
会場に入るとまず目に入るのは、フェナキスティスコープ(驚き盤)をはじめとする様々な古典的視覚装置。小さな隙間から回転盤を覗くと、描かれた静止画がまるで生きているかのように動き出します。当たり前のことのように思えますが、映像があまりに一般化した今日、我々は「ものを見る」という行為の神秘性についてどれだけ意識しているのでしょうか。アナログ感の漂う初期アニメーションは、現代を生きる我々に改めて視覚の不思議さと面白さを強烈な“感覚”として思い出させてくれるような気がします。
今回の展示の核となるのは石田尚志の映像作品。中でも特に印象的な2001年制作「フーガの技法」は、J・S・バッハの同題曲を有機的な曲線と光の舞踊によって表した映像作品です。綿密な計算に基づいて原画を楽譜の構造へ重ね合わせ、一コマごとに撮影。この作品を支えるのは、一方的な古典音楽への憧憬というよりはむしろ時代や媒体を超えた異物同士の静かなる欲情であり、感傷と神秘に満ちた旋律、線と光の抽象表現の協演は“異質の溶け合い”のみが生み出す圧倒的な陶酔と歓びを感じさせます。一瞬一瞬が多様な発見に溢れ、必然のような偶然のような、奇しき感動が心を奪います。
作品数はそれ程多くないものの、はじめから終わりまで、濃密で心地好い時間を堪能できる展示でした。来月7日まで開催しているので、機会があればぜひ訪れてみてください。
Text by NANASE
2009年、音楽回想。

あけましておめでとうございます。ついに2010年突入ですね。響きが未来世界だ…と思ってしまうのは私だけでしょうか?(笑)
昨年末になりますが、人生で初めて「その年に聴いた音楽を振り返る」ということをしてみました。iTunesのプレイリスト機能を使って2009年によく聴いた音楽をCD1枚にまとめるのです。厳選の結果、私の2009年ベストソングは以下18曲に絞られました。PP BOOKSTOREを代表する音楽好き・早崎さんに教えていただいたアーティストもちらほら。
1.Perpetuum Mobile/高木正勝
2.Sexy Boy/Air
3.Idiot/James Holden
4.Noah's Ark/CocoRosie
5.Green Grass/Cibelle
6.Etude,Op.10,No.5 In G Flat(Black Key)/Vladimir Horowitz
7.Tricycle/Psapp
8.Julia/The Beatles
9.Blessed Brambles/Múm
10.Fire,Fire/Double Famous featuring Leyona
11.帰って来たヨッパライ/ザ・フォーク・クルセダーズ
12.幸福な朝食 退屈な夕食/斉藤和義
13.jelly fish/My Little Lover
14.Cruel Park/原田知世
15.Himitsu No Hako/Eberg
16.Schumann:Kinderszenen,Op.15 - About Foreign Lands&Peoples/Martha Argerich
17.おとなになんかならないで/曽我部恵一
18.サボテンの花/チューリップ
音楽を振り返ることは、自分用の日記を読み返すことによく似ています。例えばその曲を聴いていた6月頃の帰り道の、柔らかな雨の匂いや凛とした空気、葉を躍らせる水滴の弾み、その瞬間心の中で駆け巡っていた様々な感情…そんなものたちがまるで昨日のことのようにありありと思い出され、忘れていた感覚が瑞々しく蘇ってくるのです。
“聴くこと”を楽しくする要素には、音楽としての完成度はもちろん、それと同じ位情景や感情といった“自分だけの色”のようなものの存在があると思います。人は音楽を聴く際、音そのものを楽しむのと同時に各々の心の奥底にある多様な感情や情景を思い描いたり(それもほとんど無意識的に)、周りの環境を記憶したりするものです。同じ曲を何度も聴いていると、諸々の記憶あるいは変化してゆく一瞬たちが一粒一粒の音符に絡みついて、その音楽が不思議なほど近く、濃く、愛おしく感じられることがあります。それらの要素は常に躍動・変容しながら音楽に重厚さと多様な輝きを与えます。私はそういう音楽の楽しみ方が好きです。
今回やってみてとても面白かったので、これからは毎年末に1年分の音楽をまとめようと思います。10年、20年と続いたら楽しいのですが。興味のある方がおられましたら、2009年の記憶が新しいうちにぜひ一度お試しください。きっと色々な発見があることと思います。
Text by NANASE
かいじゅうたちのいるところ
【BOOK REVIEW】

モーリス・センダック『かいじゅうたちのいるところ』神宮輝夫訳(1975年,冨山房)
こんにちは。皆さんはよいクリスマスを過ごしましたか?私はというとまさかのインフルエンザに倒れ、とても切ないクリスマスでした…。まだまだ流行っているようですので、皆さんウイルスにはどうぞお気をつけください。
さてさて。今回ご紹介するのは、モーリス・センダックの名作絵本『かいじゅうたちのいるところ』です。もうすぐ映画化作品が日本公開されるとのことで、久しぶりに読み返してみました。
物語の冒頭、主人公の少年マックスは夜に狼の着ぐるみを着ていたずらをします。お母さんに怒られて寝室に放り込まれたマックスは、いつのまにか不思議の世界に入り込んでいきます。どこかから運ばれてきた船に乗ってどこかから打ち寄せてきた波の上を何日も何日も彷徨い、そうして1年と1日が過ぎた頃、ついにかいじゅうたちの世界にたどり着くのでした…
私が感動するのは、マックスが不思議の世界に入り込んでいくときの演出です。最初は広かった絵の周りの余白部分が、ページをめくる度にどんどん狭まって、マックスが完全に異界に入り込んだとき、ついに余白がなくなる。少し気味が悪いような、心からわくわくするような。現実と幻想がじわじわと交じり合っていく様子を、実に見事に表現していると思います。
マックスとかいじゅうたちが「かいじゅうおどり」を踊るシーンも面白い。突然文字が一切なくなり、ページいっぱいにかいじゅうたちの奇妙なダンスが広がります。小さな頃、いつもこのシーンが楽しみで楽しみで仕方ありませんでした。かいじゅうのギョロっとした目や鋭い爪や牙、生々しい鱗の描写なんかを見ると、心の奥の方がぞわーっとして、何だか新鮮な満足感に満たされるのです。“怖いもの見たさ”みたいなものでしょうか。この独特な迫力は他の絵本ではちょっと味わえません。私は、こういった圧倒的な幻想体験こそ子どもにとってとても大切なものだと思っています。
映画を見る前にまずは原作の世界を存分に楽しんでおきたいところ。著名な絵本なので読んだことのある方も多いかと思いますが、この機会にもう一度目を通されてみてはいかがでしょうか。
Text by NANASE
“かぎりなく死に近い生”

写真:2009年3月,マケドニアの肉屋にて撮影。
「死」とは一体何なのでしょう。私は最近、専らそのことについて考えています。どんな生物であっても、生きている限りいつか必ず死は訪れます。考えてみれば全く当たり前のことなのに、合理性と快適さに囲まれた現代社会においてその事実はあまりにも遠く感じられる気がします。パック詰めにされた切り身魚から、それらがかつてあの果てない大海原を悠々と泳いでいた姿を想像するのは思う以上に困難です。
現代社会においてしばしば「死」は「生」と強引に切り離され、それらはまるで対極にあるかのように描かれます。そこには「死のリアリティ」というものがありません。だけど私は最近、「生」と「死」は本質的に不可分であって、両者は人知などを遥かに超えたある種の強い“絆”の中に存在するのではないかと思えてならないのです。
(私も含めて)きっと多くの人が、上の写真のような生々しい「死」を見ると自然と目を覆いたくなるし、今食べているハンバーグと生きている豚や牛は違うものだと信じ込んでいるでしょう(もちろん頭では分かっていても…)。それは悪いことではないと思います。悪いことではないけれど、私はただ不思議なのです。人間はなぜこれほどまでに「死」に向き合うことを恐れてしまうのだろう?と。
『かぎりなく死に近い生』※という本の中で布施英利は、人が死んでから灰になるまでの九段階を描いた鎌倉時代の書物『九相詩絵巻』を紹介しながら、自身の死生観を述べています。
人は、生物は、生まれながらにして死が始まっているのだ。生と死の間には明確な境界などなく、それは同時に存在する。人生というのは、その生と死のからみあいのなかにある。
布施はまた、現代の日本社会において極端に「死体が隠されている」状況を憂いています。江戸時代以降日本では都市化への信仰によって「自然の露出」が忌み嫌われ、死体やそれに関わる人々が社会の外に排除されている。まるでそれがそこに存在しないかのように、と。これを考えると、昨年の『おくりびと』のアカデミー賞外国語映画賞受賞は日本人が意識する以上に日本社会にとって意義深いことであったのではないかと思います。
確かに「死」は怖いものです。だけど、それに向き合うことは「生」に向き合うことと同義だと思います。この世界に生きている限り、私は「死」についてもっと知りたいし、もっと考えたいのです。恐怖や不条理を超えた所にある「死」の本質とは何なのでしょうか?うーん。果たしてこの壮大すぎる問いへの回答を生きているうちに見つけられるのか甚だ疑問ではありますが…。
※荒俣宏責任編集『かぎりなく死に近い生―命の思想、死の思想』(1994年,角川書店)
Text by NANASE
犬養道子『人間の大地』
【BOOK REVIEW】

犬養道子『人間の大地』(1983年,中央公論社)
少し前になりますが、11月20日は「世界こどもの日」でした。この日は今からちょうど20年前、国連総会で「子どもの権利条約」が採択された日にあたります。
私は「世界こどもの日」のニュースきっかけに、久しぶりにある本を開きました。南北問題、東南アジアのボート・ピープルの実情などを記した犬養道子のルポルタージュ『人間の大地』です。初めて読んだのは、中学生1年生のときだったと思います。目を覆いたくなるような悲惨な記録の連続に強い衝撃を受けたと同時に、人間としてこの世に生まれ、死ぬまで生きていく意味について、深く深く考えさせられました。以来、私は片時だってこの本のことを忘れたことはありません。
本書の中でも、特に心に残っている箇所があります。それは、犬養氏が1970年代末インドシナの難民キャンプで出会った“子どもでなくなってしまった子ども”のエピソードです。
紛争で家族と逸れ、一語も発さずたった一人で空を見つめる子ども。その子は食べ物はおろか、薬も流動食も口にしようとはしませんでした。衰弱しきった身体はいくつもの病気を抱えており、ついには医者も匙を投げました。そのとき、一人のアメリカ人ボランティア青年・ピーターがその子をただ「抱きしめる」ことをはじめたのです。
子の頬を撫で、接吻し、耳もとで子守歌を歌い、二日二晩、ピーターは用に立つまも惜しみ、全身を蚊に刺されても動かず、子を抱きつづけた。
三日目に―反応が出た。
ピーターの眼をじっと見て、その子が笑った!
ピーターが感動に打ち震えながら食べ物と薬を子の口に持っていくと、子はそれを食べたと言います。
このエピソードを読んだとき、私は人間の持つ愛の底深さを知りました。「抱きしめる」というただそれだけの行為が、どれだけ人を勇気づけ、生きる力を与えるのか。人は皆、絶対的な存在肯定を与えてくれる誰かの温もりを求めているのです。その後回復が確実になった子を見て、ボランティアの主任が言った言葉が胸に響きます。
「愛こそは最上の薬なのだ、食なのだ……この人々の求めるものはそれなのだ……」
26年前に本書が刊行されてから、世界を取り巻く状況は著しい変化を遂げました。しかし、世界には依然として貧困や飢餓、人身売買、児童労働など、子どもをめぐる問題が山積しています。それどころか、加速するグローバリゼーションによって1つの問題がいくつもの問題と相互作用を持つようになり、その複雑さはますます度合いを高めています。本書に収載された統計やデータは過去のものですが、ここに提示される問題意識は、決して過去のものではありません。今を生きる私たちが、今こそ、考えなければならない問題なのだと思います。本書を読み返して、その思いを新たにしました。
Text by NANASE
動物写真家・星野道夫
【BOOK REVIEW】

『星野道夫の仕事(全4巻)』(1998年、朝日新聞社)
大都会の片隅のとある図書館。何気なく表紙をめくった途端、私の目の前には、茫漠としたアラスカの大自然が広がりました。
人一人いない広大な大地。厳かに聳え立つ巨大な山々。純白の雪原を走るカリブーの群れ、お互いを温め合うように寄り添うシロクマの親子…
写真としての迫力も然ることながら、ページに織り込まれた言葉の一つ一つも力強い。決して写真の説明ではない、瑞々しい思惟の断片。特に印象に残ったのは、彼がこれ程までに敬愛した“自然”について語ったこの言葉です。
人間がどれだけ想いを寄せようと、相手はただ無表情にそこに存在するだけである。
どれだけ慣れ親しんだような気になっても、自然の中で人間だけが特別になることはない。クマと私、どちらが死んだとしても、それが自然というものなのだ。長い時間をかけて自然という“奇跡”に向き合ってきた星野さんの言葉は、私の心へとてもまっすぐに響きました。
日本を代表するジャーナリストの一人、柳田邦男も著書の中で星野道夫の写真と言葉の力について語っています。
写真がシーンの発見であるように、言葉は思索の発見である。(中略)彼にとって、写真と言葉はそれぞれに独立した不可欠の表現手段であると同時に、共鳴し合いそれぞれの意味づけを二乗倍深め合う表現手段だったのだ。
とても人気の高い写真家なので、作品をカレンダーやポストカードで目にする機会は多いと思います。しかし、写真集という「物語」に触れることによって初めて見えてくるものがある。私は彼の言葉に触れ、そう確信しました。
Text by NANASE
ブリキのおまるにまたがりて
【BOOK REVIEW】

長新太『ブリキのおまるにまたがりて』(1974年初版/2008年復刻,河出書房新社)
こんにちは。最近めっきり寒くなってきましたね。先日とあるお店で「トウガラシ成分・カプサイシン加工の手袋!」とやらを見かけました。確かに暖かそうではありますが…もしかして、やっぱり、舐めたら辛いのかしら…?ドキドキ。
さてさて。今日ご紹介するのは、ナンセンス絵本の巨匠・長新太さんのエッセイ…いや、正確に言えばエッセイではないのかもしれません。本書の帯によれば「絵本?+エッセイ?=絵ッセンス?」とのこと。
それもそのはず、この本、ただの本ではありません。見所はまず、冒頭に収載された「おまるのいろいろ」。電車式、ガニマタ用、うずまき型、親指サイズなどなど、一体どこからこんな発想が…!と思ってしまうような色々な形態のおまるを、独特のゆるーいイラストと味わいのある丸文字が描き出します。
ほかにも、物の切断面の恐ろしさと面白さについて綴った「なるほど、ポキン」、へそに住みついた虫人間「へそのごま吉」の話、星の王子さまやジョン・ケネディといった訳の分からぬ人々が訳の分からぬ会話を繰り広げる「座談会はお好き」などなど、随筆と小説と絵本と巨大な妄想がごちゃごちゃに交じり合った奇抜な企画が満載です。
絵本にも言えることですが、彼の作品の最大の魅力はやっぱり“訳がわからない!”というころではないでしょうか。理屈や道徳を超えた極めて自分勝手な人間の妄想というものの面白さを、とても素直に思い出させてくれる。ページをめくった瞬間から読者はもう、迷路のような長新太ワールドの住人です。心が折れそうなときやめげてしまいそうなとき、長さんの絵や文は、いつも心の奥の奥の方にやって来て“生きてていいのだ!”という圧倒的な存在承認を与えてくれるのです。
テキストを書いていたら、絵本を読み返したくなってきました。まだまだ寝れそうにない、秋(冬?)の夜長なのでした。
Text by NANASE